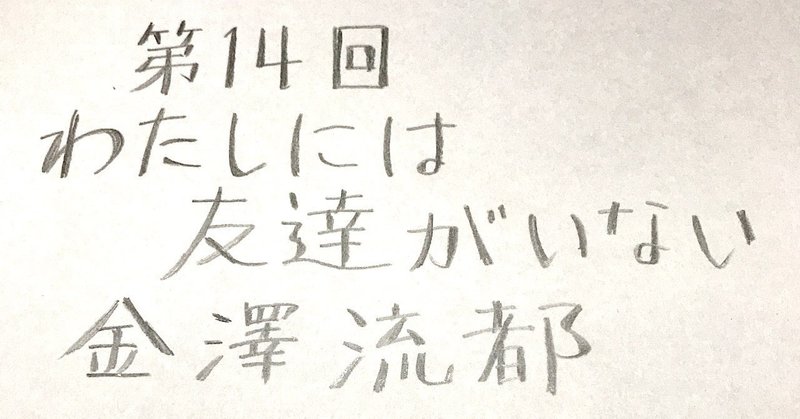
アラサー女が将棋始めてみた 第14回
第14回 「わたしには友達がいない」
今回は、将棋の話はいったん置いておいて、友達のことを書いてみようと思う。
結論から言うと、わたしには友達がいない。少ないとかではなく、いないのだ。
フェイスブックを開けば中学のクラスメイトの名前が並んでいる。だが彼らは友達でもなんでもない。ただ近況を確認できるというだけだ。ほぼ全員都会にいるし、地元にいる何人かはほぼフェイスブックなんか見ちゃいない。
だからフェイスブックに表示されるのは、都会にいるやつらの「フェスに行ってきた」だの「おしゃれなカフェに行ってきた」だのの自慢話ばかりだ。そんなものは羨ましいとは思わないし、シェアされても嬉しくない。
フェイスブックを見る限り、かつてのクラスメイトたちは次々結婚している。わたしも自分の結婚については諦めているが、もしクラスメイトの結婚式に呼んでもらえれば、祖母が買ってくれた素晴らしい振袖を着る機会もあるだろう。
でもわたしにはクラスメイトに渡すご祝儀を包む経済力がない。だからめでたいことに呼んでもらうことは諦めている。ちょっと羨ましく思いながら、まあいいや、と無視している。
そういうふうに過ごしていたのだが、ある日家族とご当地グルメを食べられる地元のイベントに行ったとき、その会場でボランティアの中学生を引率している中学三年のときの担任教師に出くわした。
その、昼ドラの悪役美男子みたいな顔をした先生は、わたしを見つけて嬉しそうに話しかけてきた。そして、
「かねじゃ(これは中学のころからのあだ名である)、クラスのやつの結婚式に呼ばれて行ったらその会場で『かねじゃどうしてるかな』ってみんな言ってたよ」
と言ったのである。
驚いた。あいつらがわたしのことを気にしていたなんて、とわりと真剣にびっくりした。あいつらはもうわたしのことなんて完全に忘れていると思っていたからである。
だけれどそれで友達がいるのだ、とは思わなかった。実際に会って話したり、遊んだりしたわけではないからである。
二十代前半くらいのころは、かろうじて遊ぶ友達がいた。年二回くらい互いの家を行き来して、ポケモンやらモンハンやらをしていたちょっと遠くに住む友達がいたし、一緒にコスプレする友達もいた。
当時、わたしはコスプレに凝っていて、驚いたことにいまより十キロばかし痩せていたのである。それでももちろんモデル体重とかそういうレベルではなかったが、『ZONE‐00』という漫画に出てくる白百合姫というキャラクターや、『ヘタリア』という国を擬人化した漫画に出てくる、フリフリの服を着たリヒテンシュタインのコスプレを、コスプレイベントに参加して着ていた。可愛い服を着た女の子に憧れるという変な体質があったのである。
それは小学生のころマリオパーティをやるときだいたいデイジーを選んでプレイしていたのと同じ理由だと思う。ピーチ姫よりデイジーが好きだった理由はよくわからない。ちなみにマリオパーティは超下手くそで、一回も一位を取ったことがない。桃鉄も然りである。
一緒にコスプレをしていたその友達は、身長が170センチオーバーのすらりとした子だった。一緒にコスプレをしようよと無理を言って、彼女には白百合姫のお供の犬の魔物や黒薔薇(いかがわしい名前だがイケメンキャラである)の人間の姿のコスプレをお願いした。彼女はとても手先が器用で、衣装を自作した。
一方わたしはお小遣いをけちけち貯めて、中国製の衣装を通販したのだった。
ポケモンやモンハンで遊んでいた友達に誘われて、『東方プロジェクト』の霊夢とか、進撃の巨人のアルミンの衣装やウィッグを買ったこともある。その友達は転勤族で、電車で三時間のところに引っ越してしまったので、結局コスプレイベントの類には参加しなかったし、そのうち行こうね、と言っているうちに喧嘩別れしてしまった。
今思うと、そんな方法でしか友達をつないでおけなかったのは、幼かったとしか言いようがない。お小遣いを潤沢にもらえる友達と違って、一着七千円の調査兵団衣装セットを買うのはとても勇気のいることだった。それでもその友達と一緒にいたくて、それを買ったのである。
でもポケモン友達と喧嘩別れして、身長170オーバーの子とも疎遠になり、わたしはコスプレ衣装やウィッグをかたっぱしからフリマアプリに突っ込んだ。
なんてばかばかしい金の使い道だったんだろう、と思うけれど、これは勉強だったのだと思うことにしている。あのころは若かったのである。若気の至りだったのである。まだ自分が可愛くなれると思っていた。いまはそうは思わない。
他には、ときどき酔っぱらって夜中のニューヨークからフェイスブックのメッセンジャーで電話をかけてくる、小学校中学校と同級生だった元丸刈り野球少年の男子もいるが、そいつだって友達と呼べるかは怪しい。酔って話す相手がいないらしく電話を掛けてくるのだが、そいつは
「お前の人生はさあ、最高に面白いからさあ、お前の人生を書けよ」
とゴタクを並べてくる。わたしがそんなに面白い人生を生きているならそいつから見物料を取りたい。それから電話口でカノジョの名前とわたしの名前をいちいち間違えるのもやめてほしい。
たぶん、そいつはもう坊主頭ではなくなっていて、会っても顔を認識できないだろう。最近のそいつを知るやつらによると「ディズニーアニメの王子様」ないし「インド人」に似ているらしい。
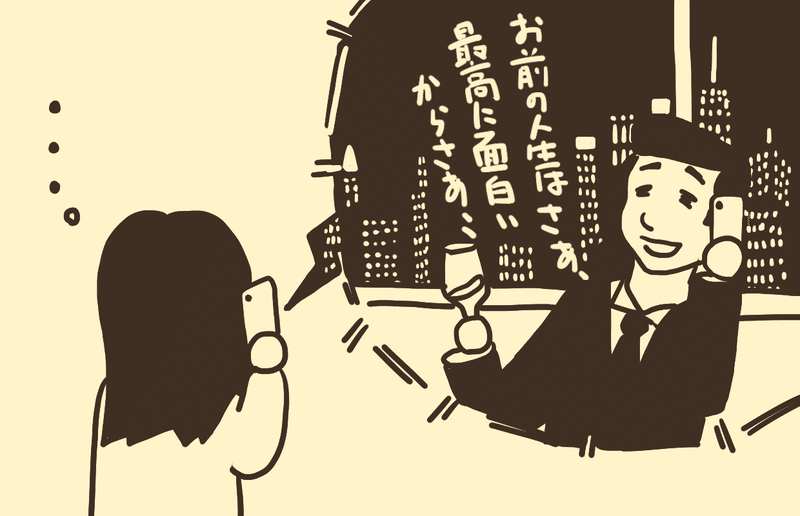
そういうわけで、リアルな友達はいない。ツイッターで親しくしている顔も知らない人たちが、しいて言えば友達なのかもしれないし、もうすぐサービスが終了してしまう某ソシャゲのじょうろを送り合うだけのフレンドも友達と言えるかもしれない。
そういう、ある意味孤独な状況だったから、公民館の将棋道場に初めて行って「それじゃあ棋力はどんなものか調べてみようか」と、支部長さんに一瞬でやっつけられたときのことが忘れられない。公民館でおじさんたちに将棋の技術を教えてもらえることがうれしくてたまらない。
おじさんたちは私生活の点では友達ではないかもしれない。しかし、盤を挟めば、だれだって友達なのではないか、とわたしは思うのである。
わりと普通とは違う人生を歩いてきた自信はある。中学校は保健室登校だったし高校は一年生を二回やって辞めた。ほんのいっときアルバイトらしいアルバイトをしたけれど、その後は家族が許してくれることにかまけてずっと労働せず公募用の小説を書いて、新人賞に投稿するも箸にも棒にも掛からぬ、という生活をしていた。
そもそもその「普通」が何なのかはよく分からないが、「15で高校。18で大学。22で社会人」と電車みたいにみんなと同じタイミングで乗り降りする人生を普通とするなら、わたしはそれから大きく外れている。だからニューヨーク野郎に「お前の人生は面白い」と言われるのだろう。そして、そういう人生だから、友達になれる人間の母数は極端に少ない。
友達がいないことを、特に苦だとは思わない。むしろ誰かとつるんでいなければなにもできないというのは愚かしいと思う。
でもときどき、だれか遊んでくれないかな、とは思う。だから、公民館に行ってみようと勇気を出してよかった、と思う。日曜午後の公民館にいけば、確実に誰かが将棋の相手をしてくれて、ワクワクする戦いができるのだ。
あるいは、だれか一緒に遊んでくれるひとが欲しくて、公民館に行ったのかもしれない。将棋というのは一見すると難しくて「道」の類のものに見えるが、ある日とあるおじさんがずばり「まあ将棋はボードゲームだから楽しくやろう」と言ったのだ。どんなに難しい顔で考えて指しているとしても、将棋はボードゲームなのである。楽しくできるものなのである。
友達がいないのはハタから見れば悲しいことかもしれない。でもわたしは楽しんで生きているし、加藤一二三先生の言葉を借りるなら「よろこんでいきる」人生を生きているつもりだ。それにこの先だれかと友達になるかもしれない。わからないけれど明るく生きようと思う。悲しいことを思い出してしょげるのは、馬鹿らしいからだ。
イラスト:真藤ハル
Profile/金澤流都(かねざわるつ)
平成ヒトケタ生まれ。統合失調症を拾い高校を中退。その後ほんのちょっとアルバイトをしただけで、いまはライトノベル新人賞への投稿をしながら無職の暮らしをしている。両親と猫と暮らしている。
Twitter https://twitter.com/Ruth_Kanezawa
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

